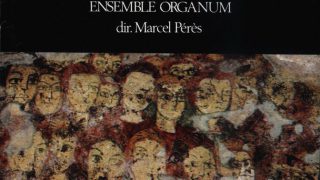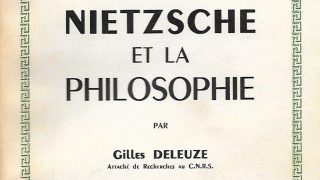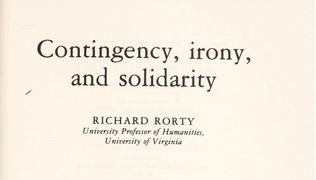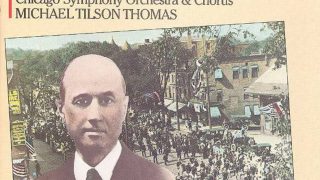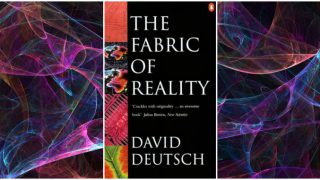概説
『吉野葛』は日本の小説家、谷崎潤一郎(1886–1965)による中編小説である。1931年に雑誌『中央公論』に掲載された。
制作の背景
谷崎潤一郎は1886年に東京で生まれた。谷崎は1910年代(明治末期から大正初期)に、短編小説『刺青』(1910年)に代表されるようなマゾヒズムや魔性の女などのスキャンダラスな題材を扱ったモダンで耽美的な小説群によって作家としての地位を確立した。
1923年の関東大震災後に関西(京都、兵庫)に移住した谷崎は、1920年代(大正後期から昭和初期)に『痴人の愛』(1924年–1925年)などの風俗小説で注目を集めた。
その後、『蓼喰ふ虫』(1928年–1929年)を転回点として、谷崎の作品は関西の伝統文化や日本の古典文学の再発見によって特徴づけられる、いわゆる「古典回帰」の作風へと変化した。『春琴抄』(1933年)や『陰翳礼讃』(1933年–1934年)は1930年代の古典回帰時代の有名作であるが、『吉野葛』(1931年)はこの時期のもう一つの傑作である。
プロットの概要
『吉野葛』は東京在住の小説家である語り手の一人称視点から書かれている。語り手は20年前の秋に友人と吉野を旅行したときの体験を回想する。
吉野は奈良県の中央、大阪の東に位置する、豊かな自然と名所旧跡で知られる地域である。南北朝時代(1337年–1392年)には南朝は吉野を拠点としていた。吉野川の上流に位置する国栖(くず)の里は、古来から伝わる手漉きの和紙で有名である。
その当時、語り手は1392年の南北朝合一後の吉野を舞台に南朝の末裔の秘史を描く歴史小説を構想していた。
語り手の高校時代の旧友の津村は大阪に住んでいたが、吉野の国栖に親戚がいた。
津村によると国栖の人々は南朝の遺臣の血統と縁故関係があり、今でも機械を使わずに手漉きで紙を作って生計を立てているという。
津村はある目的のために国栖の親戚を訊ねようとしていた。津村に誘われて、語り手は歴史小説の取材のために津村とともに吉野を訪れる。
吉野を旅行中に津村は幼い頃に亡くした母への思慕について語り始める。津村の母に対する思慕は理想の女性に対する憧れでもあり、津村の心の中では土着の稲荷(狐)信仰とも結び付いていた。
解説
『吉野葛』は一般的に、谷崎が「吉野を舞台にした歴史小説を書こうとして失敗した」自身の経験に基づいて書いたエッセイ風の小説として捉えられている。
本作は随筆または紀行文のようなとりとめのない文体で書かれており、歴史的な文書や民間伝承、古典文学、歌舞伎『妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)』、謡曲『二人静(ふたりしずか)』、箏曲『狐噲(こんかい)』などの伝統芸能に対する参照を数多く含んでいる。
短編小説『母を恋ふる記』(1919年)に見られるような「母恋い」の主題は谷崎の主要な主題群の一つであるが、この『吉野葛』にも「母恋い」の主題が挿話の一つとして含まれている。
『吉野葛』のとりとめのない散文は、物語に引き寄せられつつも物語を語ることを自虐的に回避しているような印象を与える。読者は「引用の織物」(ロラン・バルト)の中で物語の不可能性に直面させられる。
散文小説における物語の回復と解体という両義性を主題化した日本の小説家、中上健次は、エッセイ「物語の系譜: 谷崎潤一郎」(1979年)において『吉野葛』を谷崎の最高傑作と捉え、『吉野葛』における物語の自壊(内破)をマゾヒズムとの関係で論じている。
日本の批評家、蓮實重彦は著書『魅せられて: 作家論集』(2005年)の中で、「『書く』ことによる『語る』ことの侵食」という表現を用いて『吉野葛』のテクストを分析している。
出版履歴
『吉野葛』は1932年に中央公論社より刊行された『盲目物語』に収録された。

その後、1937年に創元社により「潤一郎六部集」の一冊として単行本化された(限定370部、写真入り)。

翻訳
英語
- “The Secret History of the Lord Musashi and Arrowroot”, Anthony H.Chambers, Alfred A. Knopf, 1982

- ‘Yoshino Arrowroot’ by Jun’ichirō Tanizaki: A New Translation, Jason James, the Daiwa Anglo-Japanese Foundation, 2020: https://dajf.org.uk/news/yoshino-kuzu-by-junichiro-tanizaki
フランス語
- “La Vie secrète du seigneur de Musashi (suivi de) Le Lierre de Yoshino”, René de Ceccaty et Ryôji Nakamura, Éditions Gallimard, 1987

- “Œuvres I”, Jacqueline Pigeot, Éditions Gallimard, 1997

スペイン語
- “La vida enmascarada del señor de Musashi; Enredadera de Yoshino”, Fernando Rodríguez-Izquierdo, Edhasa, 1989

イタリア語
- “Yoshino”, Adriana Boscaro, Letteratura universale Marsilio, 1998

簡体字中国語
- “春琴抄/吉野葛”, 林少華, 青島出版社, 2019