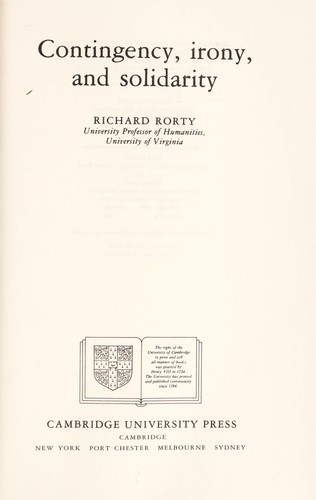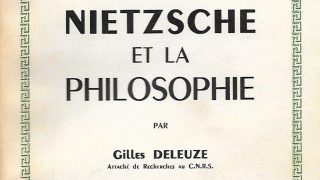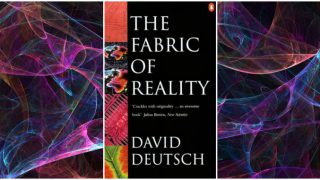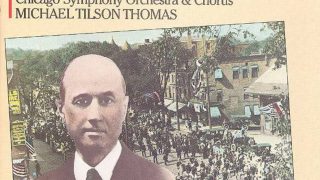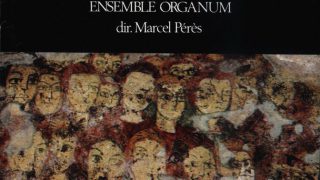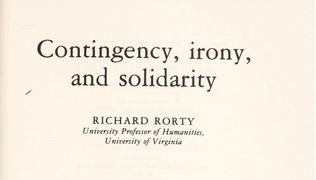概説
『偶然性・アイロニー・連帯(Contingency, Irony, and Solidarity)』は、アメリカ合衆国の哲学者、リチャード・ローティの本である。ローティがユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(1986年)とケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジ(1987年)で行った2組の講義が基になっている。本書は1989年にケンブリッジ大学出版局から出版された。
ローティはジョン・デューイのプラグマティズムや分析哲学、ポストモダン哲学などに影響を受けたネオプラグマティズムの立場から近代哲学史を批判的に再検討し、現代の哲学や政治に関する議論に広範な影響を与えた人物として知られている。
ローティは本書で、人々が自分の正しさを他者と共有することが困難になった現代のポストモダン状況において「人間の連帯」はいかにして可能かというテーマを扱っている。
ローティによると、ヘーゲル以後の歴史主義的な哲学においては人間の言語や良心、共同体は歴史的な偶然性の産物と見なされ、客観的な真理や普遍的な人間性といったプラトン主義的な観念は棄却される。
その結果として、知識人は自分の信念や欲求が歴史的な偶然性の産物であることを知っているため、自分の正しさに対して常に疑いを抱くことを強いられる。ローティはそれを「アイロニズム」と呼んでいる。
ローティは「リベラル」という言葉の定義をラトビアのリガ生まれの政治学者のジュディス・シュクラーから借りている。シュクラーによると、残酷さこそがわれわれがなしうる最悪のことだと考える人々がリベラルである。
ローティによると、アイロニストにとっては私的なものと公共的なものを統合する理論は存在せず、自己創造の欲求と人間の連帯の欲求は共約不可能である。それゆえ、政治的にリベラルであろうとするアイロニストは私的な自律と他者に対する残酷さの回避をいかに両立させるかという問題に直面する。それは、リベラルなアイロニズムはいかにして可能かという問いである。
ローティは以上のような見地から、リベラルなアイロニストにとっての「リベラル・ユートピアの可能性」を探る。
ローティは、人間の連帯は他者に対する残酷さ、すなわち他者の苦痛と屈辱に対する感性の拡張によって達成されるべき目標であると主張する。
「私のいうユートピアにおいては、人間の連帯は『偏見』を拭い去ったり、これまで隠されていた深みにまで潜り込んだりして認識されるべき事実ではなく、むしろ、達成されるべき一つの目標だ、とみなされることになる。この目標は探究によってではなく想像力によって、つまり見知らぬ人びとを苦しみに悩む仲間だとみなすことを可能にする想像力によって、達成されるべきなのである。連帯は反省によって発見されるのではなく、創造されるのだ。私たちが、僻遠の他者の苦痛や屈辱に対して、その詳細な細部にまで自らの感性を拡張することによって、連帯は創造される。」(「序論」、齋藤純一・山岡龍一・大川正彦訳、岩波書店、2000年)
概要
本書は「序論」と「第I部 偶然性」、「第II部 アイロニズムと理論」、「第III部 残酷さと連帯」の三部で構成されている。
第I部 偶然性
最初の3章では、ローティは人間の言語、良心、共同体が歴史的な偶然性の産物にすぎないということを論じている。
第一章 言語の偶然性
ローティはここで、ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインやドナルド・デイヴィドソンなどの分析哲学を参照しながら、言語は実在を表現=再現する媒体ではなく、世界に対処するための道具であるということを論じている。
ローティは言葉の字義通りの使用とメタファーとしての使用を区別しており、「科学革命」(トマス・クーン)は自然に関するメタファーを駆使した再記述(メアリー・ヘッセ)であると述べている。
第二章 自己の偶然性
この章は、主にジークムント・フロイトを参照しながら、良心または道徳意識の偶然性について論じている。
第三章 リベラルな共同体の偶然性
この章は、アイザイア・バーリンの『二つの自由概念』(1958年)、マックス・ホルクハイマーとテオドール・アドルノの『啓蒙の弁証法』(1947年)、マイケル・オークショット、ミシェル・フーコー、ユルゲン・ハーバーマスなどを参照しながら、政治的なリベラリズムと啓蒙の合理主義の関係を論じている。
ローティは、メタファーや自己創造といった考えを中心に据える語彙の方が、真理、合理性、道徳的な義務といった啓蒙の合理主義の語彙よりもリベラルな社会に役立つと主張する。
第II部 アイロニズムと理論
第四章 私的なアイロニーとリベラルな希望
ローティはここで、唯名論者であり歴史主義者でもあるアイロニストの概念を説明し、アイロニストの文化と形而上学の文化を対比している。
ローティによると、ヘーゲルはプラトン-カント的な伝統から袂を分かち、ニーチェ、ハイデガー、デリダへと続くアイロニスト哲学の伝統を創始した。その結果として、ヘーゲルの『精神現象学』(1807年)がアイロニストの能力のパラダイムとなった。
ローティによると、形而上学の文化では神学、科学、哲学といった学問分野が残酷さの除去に寄与することが期待されたが、アイロニストの文化では、私的な領域を専門に記述する小説やエスノグラフィといった学問分野がその作業を行う。
第五章 自己創造と自己を超えたものへのつながり―プルースト、ニーチェ、ハイデガー
この章はアイロニストの小説のパラダイムであるマルセル・プルーストの『失われた時を求めて』(1913–1927年)とアイロニストの理論(ニーチェ、ハイデガー)の比較分析を行っている。
ローティはここで、1930年代の「転回」(die Kehre)以後のハイデガーのディレンマ(形而上学批判と形而上学への回帰の)についても分析している。
ローティによると、プルーストが私的な自律と美にとどまったのに対してハイデガーは公共性と崇高さを求めて哲学を詩化し、その結果として形而上学に回帰した。
第六章 アイロニストの理論から私的な引喩へ―デリダ
この章はデリダの『絵葉書─ソクラテスからフロイトへ、そしてその彼方』(1980年)に着目して、1970年代から1980年代にかけて、理論的に語ることをやめて言語の物質性に重点を置いた難解なテクストを発表するようになったデリダの戦略について論じている。ローティはそれを私的なものと公共的なものを結びつけようとする試みの放棄として捉えている。
第III部 残酷さと連帯
第七章と第八章は、自律の探求に潜む残酷さに対して警告を発した著作家の例としてウラジーミル・ナボコフとジョージ・オーウェルを採り上げている。
第七章 カスビームの床屋―残酷さを論じるナボコフ
この章はナボコフの『ロリータ』(1955年)と『青白い炎』(1962年)を参照しながら、自らの審美主義における他者への無関心に起因する残酷さに対するナボコフ自身の恐怖について論じている。
第八章 ヨーロッパ最後の知識人―残酷さを論じるオーウェル
この章は、屈辱または人格の破壊としての拷問を描いたオーウェルの『一九八四年』(1949年)の最後の三分の一に着目して、そこに未来におけるポスト全体主義の危険性に対する警告を読み込んでいる。
第九章 連帯
ローティは最終章で、われわれは他のすべての人間存在との連帯の感覚を抱くべき道徳的な義務を負っていると主張する。
ローティによると、連帯の感覚は「われわれの一員」という考えに基づいている。「われわれ」は人類よりも小さくローカルなものを意味している。われわれは人間の連帯のために、「われわれ」という感覚を可能な限り拡張しようとし続ける必要がある。
総評
人間の連帯はいかにして可能かという本書の中心的なテーマは、人間の本性や理性と良心の普遍性といった啓蒙の合理主義の理念を措定できないわれわれにとっては一種のアポリア(難題)である。
ヒューマニズムがわれわれが実際に所属している個々の集団や共同体に根を持たない空疎な概念だとすると、われわれの他者に対する憐れみは、自己愛や共同体のエゴの延長にすぎないのか? われわれの倫理は一体何に基礎を置くべきなのか?
ローティは本書でこの倫理的相対主義の問題をリベラリズムの立場から考究している。読者に自らの倫理観についての内省を促す、刺激的な本である。
本書はジャーゴンを排した平易な言葉で書かれている。幅広い読者層に対して開かれた、読みやすい本である。
ローティが言う目標としての「人間の連帯」は、カントが『純粋理性批判』の付論で論じた「統制的理念」(regulative Idee)または「虚焦点」(focus imaginarius)として理解することができる。つまり、われわれは単一の倫理観に基づいて「われわれ」という感覚を全人類に対して拡張することは決してできないという意味ではそれは到達不可能な目標だが、倫理的な実践においては理想として有益かつ不可欠な理念である。
本書に対して寄せられる主な反論の一つは、本書が私的なものと公共的なものの分離を強調し過ぎているということである。ローティは私的なものと公共的なものの共約不可能性を強調しているが、実際には人は他者との関係を通して個人となる。本書は個人を社会的な諸関係の産物として捉える視点を欠いている。
本書におけるローティの哲学観と政治的な姿勢にはおおむね共感するが、読んでいて疑問に感じたのは、(ローティが最終章で述べている)「われわれ」の拡張が共同体の拡張主義に似ているように思える点である。
「僻遠の他者の苦痛や屈辱に対する感性の拡張」は、共同体の拡張でも他者の我有化でもない筈である。それは共同体の利害や自民族中心主義を超えた他者との出会いの過程における、「社会的諸関係の総体」(マルクス『フォイエルバッハに関するテーゼ』)としての自己の再編であるべきである。