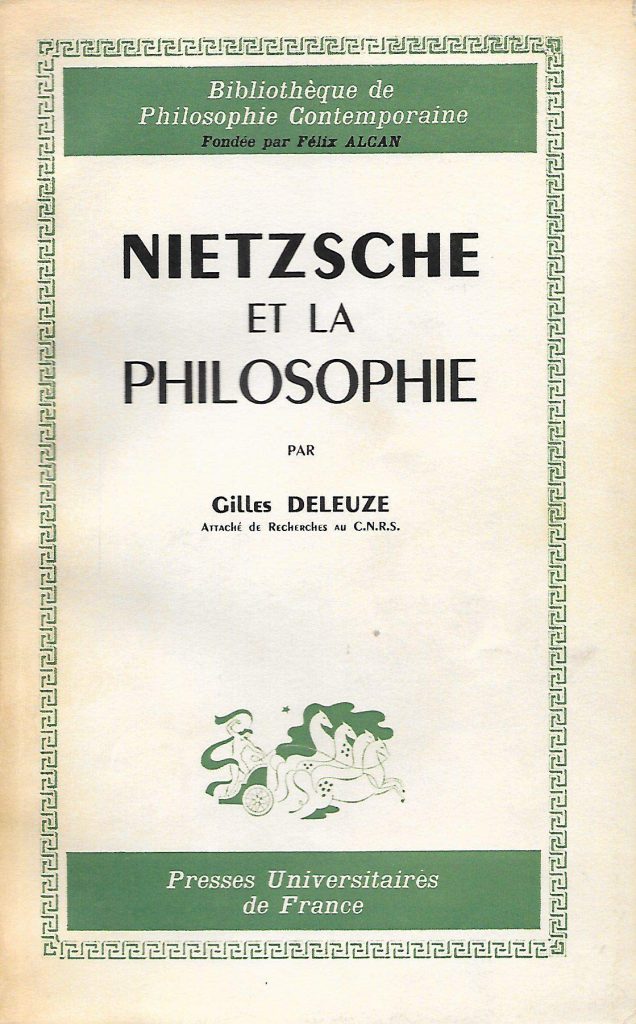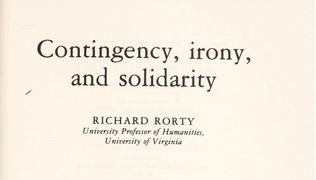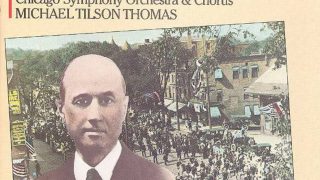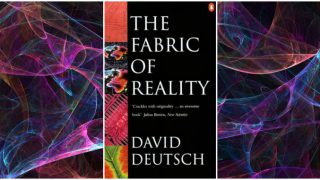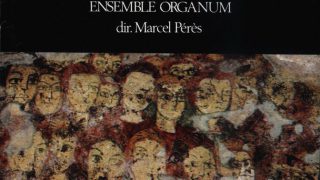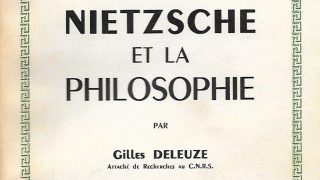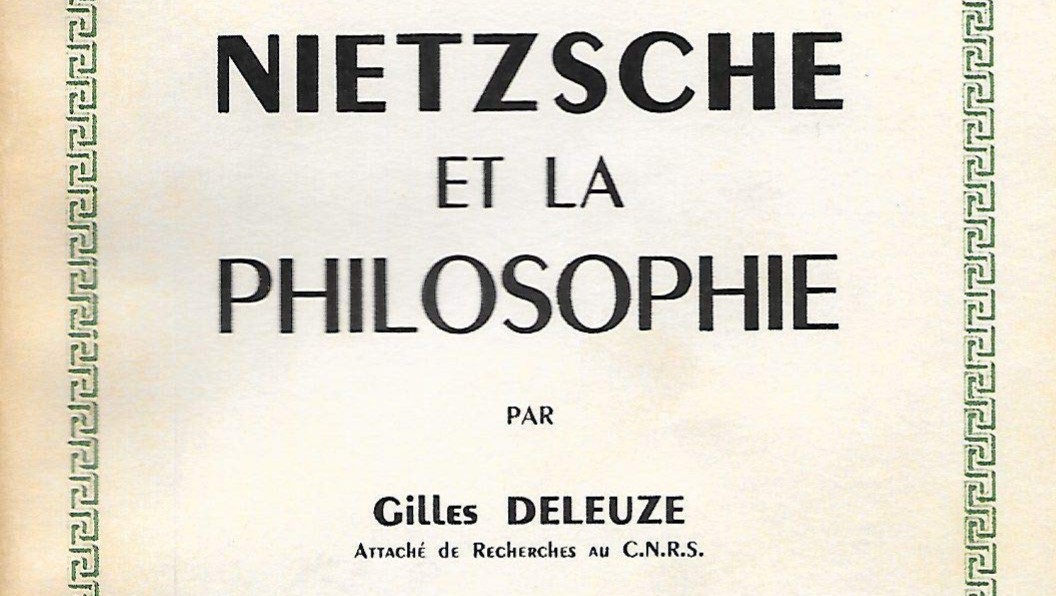『ニーチェと哲学(Nietzsche et la philosophie)』は、フランスの哲学者、ジル・ドゥルーズの本である。1962年にフランス大学出版局から出版された。
ドゥルーズが独自の理論的な視点からニーチェのテクストを解釈し体系化した本である。「力への意志(Wille zur Macht)」「永劫回帰(Ewige Wiederkunft)」「超人(Übermensch)」などの奇妙な概念を含むニーチェの文学的で謎めいたテクストを読み解くための重要な示唆を多く含んでいる。
本書は単なる解説書ではなく、ドゥルーズがニーチェを導入しつつ自説を展開している本でもあり、スピノザやベルクソンとともにニーチェからも多大な影響を受けたドゥルーズ自身の哲学への導入編としても読める。
ドゥルーズはニーチェの「能動/反動」という鍵概念に着目してニーチェを読み解いてゆく。ニーチェによると、能動的な諸力と反動的な諸力の関係が有機体を構成しており、身体の能動性・優越性に対して意識は本質的に反動的・劣等的である。ある種の人間的特質─超感性的な観念(神、来世、真理など)に依拠する形而上学 、否定的なものに駆動される思考(ヘーゲルの弁証法など)、キリスト教的な現世の生の否定(ニヒリズム)、怨恨(ルサンチマン)を共有する弱者たち(畜群)の宗教・道徳・国家による支配など─は、この意識の本質的な反動性に由来する。生の否定としてのニヒリズムは人間の条件のようなものであるから、それに抗して生を肯定する者は「超人」となる。このあたりの整理は明快である。
しかし問題点もある。たとえば、あらゆることが無限に繰り返されるという「永劫回帰」の概念は、キリスト教の終末論やヘーゲル的な目的論への批判、一回性の連続的循環としての生の絶対的な肯定を意味すると考えられるが、ドゥルーズはこれを多数多様な諸力の生成の「存在」、事象の発生原理として解釈する。
「われわれは永遠回帰そのものを、多種多様なものとその再生産との、差異とその反復との根拠である原理の表現としてしか理解できないのである。」(第二章)
ドゥルーズはニーチェを存在論に回収するハイデガーのニーチェ解釈を批判しているが(第五章の原注521)、ドゥルーズ自身もニーチェを存在論化しているのではないか。この点についてはアラン・バディウによるドゥルーズ批判でも問題にされている。
ドゥルーズの『差異と反復』(1968年)では、ニーチェはドゥンス・スコトゥス(一義的存在)、スピノザ(神即自然)、ニーチェ(生成の存在としての永劫回帰)という哲学史における「存在の一義性」の三つの契機の一つとして位置付けられ、潜在性が顕在化するというような、ベルクソンの「生の哲学」に似た統一理論に回収されてしまっているように思える。
ニーチェのテクストをハイデガーの存在論やベルクソンの「生の哲学」ではなく、スピノザ=マルクス的な唯物論の方に引きつけて読むべきではないか。その意味では、本書や『差異と反復』よりもフェリックス・ガタリとの共著─『アンチ・オイディプス』(1972年)、『千のプラトー』(1980年)─の方が、ユーモラスで現実批判的という点でむしろニーチェに近かったのかもしれない。