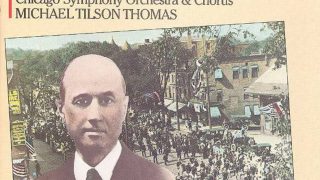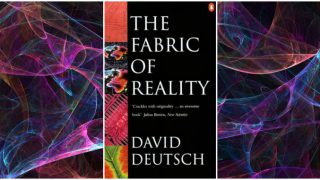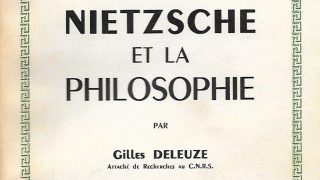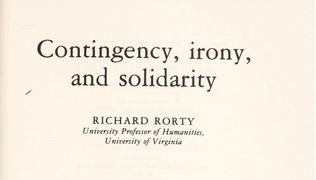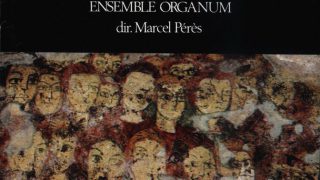『有限性の後で: 偶然性の必然性についての試論(Après la finitude. Essai sur la nécessité de la contingence)』は、フランスの哲学者、カンタン・メイヤスー(Quentin Meillassoux)の最初の本である。フランス語の原著は2006年にスイユ出版社から出版された。
フランスの哲学者のアラン・バディウによる序文が付されている。メイヤスーはバディウの高等師範学校の元教え子である。
この本は、人間は物自体を認識することはできず、人間の認識形式が現象を構成すると考えたカント以降の哲学において、数学的に捉えられる世界の客観的な実在性、人間がいなくても世界は存在した/するだろうという意味での世界の自律性をどう考えるかということ、数理的な自然科学の哲学的基礎づけのようなテーマを扱っている。
メイヤスーはこの本で、独自の思弁的な唯物論の立場からポストモダン的な相対主義、人間中心主義を批判している。これは近現代の哲学総体に関わる重要な論点であり、カント的な批判主義と科学哲学、スピノザ=マルクス的な唯物論を起点としてこの問題を考えていた自分にとっても示唆的だった。
物自体を認識不可能とするカント以降の哲学では、主観と客観、思考とモノの相関関係のみを扱っている。メイヤスーはそれを「相関主義」と呼んでいる。それはモノを直接的に思考することを放棄し、人間中心主義的・超越論的な観念論に陥っている。相関主義の枠内では、宗教の教説も科学の仮説も各集団の認識形式、間主観的な観念にすぎないということになり、どれに信を置くかは個人の自由ということになる(ポストモダン的な相対主義、信仰主義)。
この指摘はその通りだと思う。現象学は意識に対する世界の現れのみを扱い、分析哲学は言語や論理と世界の関係のみを扱っている。この本で槍玉に挙がっているのは現象学と分析哲学を代表するハイデガーとヴィトゲンシュタインだが、総じて現代哲学は、超越論的な観念論の循環回路から抜け出すことができない。
現代科学が人間の思考とは無関係に存在するであろう世界―数学的に捉えられる実在―の理解を推し進めているのに対して、現代哲学は思考からモノ自体を追放し、相関主義の閉域内で観念による観念の批判に終始している。
この堂々めぐり、「相関的循環」から抜け出し、モノ自体を直接的に思考することは可能なのか。これは現代においても未解決の哲学的な難題であり、本書も結論にまでは至っていない。
どう考えても、人間の思考がモノ自体に直接アクセスすることはできない。かといって、素朴実在論や独断論に回帰するわけにもいかない。では一体どうすればいいのか。
人間と自然の断絶を重視する立場と、人間も自然の一部と考える立場がある。近代哲学の主流やラカン派は前者、スピノザやドゥルーズは後者である。メイヤスーは前者の立場から、近代哲学史をカント以前に遡ってデカルトに回帰し、人間とは無関係に存在する世界の実在を哲学的に論証しようとする。
神の存在論的証明に基づいて数学的実在を基礎づけたデカルトに対して、メイヤスーは神に代わる「第一原理」として、世界の絶対的な偶然性、理由もなく起こることがすべてだという事実性を想定する。
ドゥルーズは『ニーチェと哲学』(1962年)で、マラルメの『骰子一擲(賽の一振りは決して偶然を排することはないだろう)』(1897年)を引き合いに出して、ニーチェの(生成の存在としての)「永遠回帰」を論じているが、メイヤスーの偶然性の必然性に関する議論は、アラン・バディウによるドゥルーズ批判を踏まえつつ、ドゥルーズの議論を批判的に参照しているようである。この文脈でメイヤスーが言及している無限面の宇宙サイコロの概念は、イメージとしては面白い。
メイヤスーによると、ポパーは科学を反証可能な仮説だと考えたが、ヒュームがいう自然の斉一性の原理(自然法則の恒常性)は疑っていなかった。メイヤスーは自然の斉一性の原理、理由律自体を疑う。
自然法則ですら理由もなく変わりうるというメイヤスーの主張は奇矯に思えるが、一定不変の自然法則や理由律の支配というのは人間側の想定にすぎず、それらが世界に内在する秩序であるという保証はないのだから、考え方としては理解できる。しかしそのような世界の偶然性を原理として考えることができるだろうか。
メイヤスーは「神なきデカルト主義」のような立場に立って数学的実在を基礎づけようとするのだが、メイヤスーの世界の偶然性についての存在論的な推論はSF的で、思考実験的な面白さはあるが、形式論理だけで世界を説明しようとする姿勢には疑問を感じた。世界の絶対的偶然性(無限に存在する世界自体の可能性)を、師匠のアラン・バディウ経由でカントールの無限集合論を援用して論証しようとしている箇所もあまり説得的とはいえない。
世界の絶対的な偶然性を「第一原理」として措定してしまうと、それはそれで一つの形而上学、神学への道なのではないか。そのような原理の存在は反証不可能である。
自然科学とコンピュータ技術の発展を背景とする今日の反人間主義は、ある種の数学的な形而上学に近づく傾向があるように思われる。そのような観念をカント的な批判的知性によって批判する必要がある。我々は結局、カント的な批判主義とポパー的な反証主義にとどまる他ないのではないか。