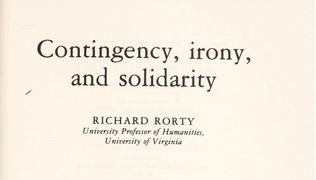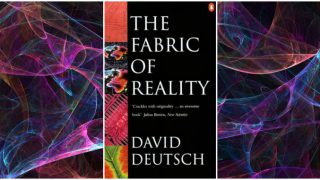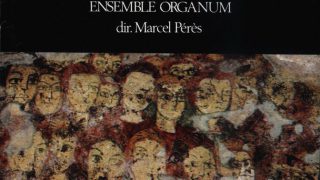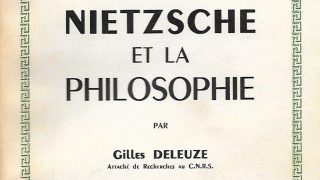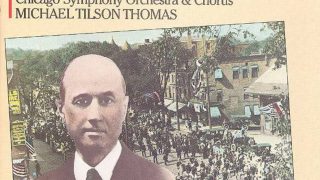概説
『カメラを持った男』(ロシア語原題: Человек с киноаппаратом / Chelovek s kinoapparatom、日本初公開時の邦題:『これがロシヤだ』)は、1929年のソヴィエト連邦のサイレントのドキュメンタリー映画である。
監督・編集はジガ・ヴェルトフ。撮影はミハイル・カウフマン。編集補佐はエリザヴェータ・スヴィーロワ。制作は全ウクライナ写真映画庁(VUFKU)とドヴジェンコ・フィルム・スタジオ。
インタータイトル(中間字幕)なし。68分。

本作は、ソヴィエト市民の都市生活のさまざまな場面を当時としては革新的な映画技法を駆使して記録した実験的な映画であり、未来派やロシア・アヴァンギャルドの影響を受けた前衛的なモダニズム映画であり、ソヴィエト社会主義のプロパガンダ映画であり、映画それ自体を題材にした自己言及的なメタ映画でもある。
本作は、カメラのレンズを人間の眼によっては見ることができないありのままの真実を捉えるためのテクノロジーツール(機械の眼)として用いる、「キノ・グラース(映画眼)」と呼ばれるヴェルトフの独自の映画技法に基づいて制作されている。
本作は短いショットの連続のみによって構成されている。劇映画や演劇、文学の要素を排除しており、プロットや脚本、セット、俳優は存在しない。
本作は速いカッティングと斬新な映画技法によって、大都市の目まぐるしい動きとダイナミズムを万華鏡のようなイメージの連続として表現している。カッティングはリズミカルで、スピードの緩急の対比がテンポの変化を生み出している。サイレント映画であるが、映画全体が交響曲のように音楽的である。機械文明あるいは工業都市を題材にした一種の映像詩として観ることもできる。
制作の背景
ヴェルトフは20世紀前半のソヴィエト連邦体制下でニュース映画とドキュメンタリー映画の監督として先駆的な仕事をしたことで知られている。
1917年の十月革命後、ヴェルトフは1918年から1919年にかけてモスクワ映画委員会の週間ニュース映画シリーズ『キノ・ネジェーリア』の編集に携わり、『革命記念日』(1918年)、『ツァーリツィンの戦い』(1920年)、『全ロシア執行委員会の扇動列車』(1921年)などのドキュメンタリー映画を監督した。
ヴェルトフは1920年代初頭に「キノ・グラース(映画眼)」と呼ばれる独自の映画技法を提唱し始める。ヴェルトフはカメラのレンズを機械による人間の眼の延長として捉え、それをテクノロジーツール(機械の眼)として用いることによって、人間の眼によっては見ることができないありのままの真実を捉えることができると主張した。
一連のショットを組み合わせることによって架空の物語を劇的に表現することを狙ったセルゲイ・エイゼンシュテインのモンタージュ理論とは異なり、ヴェルトフの「キノ・グラース」はリアリズムを主眼としていた。
ヴェルトフは「キノ・グラース」に基づいて映画を制作するために、映画監督・映画編集者のエリザヴェータ・スヴィーロワ(後の妻)、撮影監督のミハイル・カウフマン(弟)とともに映画制作集団「キノキ(映画眼)」を設立した。
その後、ヴェルトフは実験的な技法を導入しつつ、全23号のニュース映画シリーズ『キノ・プラウダ(映画真実)』(1922–1924年)や『キノ・グラース(映画眼)』(1924年)、『世界の六分の一』(1926年)、『進め!ソヴィエト』(1926年)、『11年目』(1928年)などのドキュメンタリー映画を監督し、1929年に「キノ・グラース」に基づく実験的な試みの集大成とも言える『カメラを持った男』を発表した。
ドキュメンタリー映画としての側面
『カメラを持った男』は、1920年代後半のソヴィエト連邦のモダンな都市生活を記録したドキュメンタリー映画であり、オデッサ、キーウ(キエフ)、ハルキウ、モスクワで撮影された膨大な数の短いショットで構成されている(モスクワ以外の3都市は現在のウクライナに位置している)。
本作は以下のようなソヴィエト市民のさまざまな生活風景を捉えている。
街頭で寝ている人々。
女性が朝起きて服を着て顔を洗う(この場面は明らかに演出されている)。
工業都市の風景: 工場、工場の機械、煙を空に吐き出す工場の煙突、炭鉱、製鉄、ダム、タイプライター、ミシン、レジ、電話交換、たばこ製造、エレベーター、新聞輪転機、美容院、洗濯、靴磨き。
運輸と交通: 町を行き交う人々、交差点、路面電車、線路を走る列車、自動車、バス、馬車、飛行機、船。
市場、ショーウィンドウ。
婚姻届と離婚届、新婚の夫婦、出産、戦死した兵士の葬列。
救急隊と消防隊。
余暇活動: 浜辺での日光浴と泥浴、水泳教習、パブでビールを飲む人々、ボードゲーム、メリーゴーラウンド、射的場、ピアノの演奏とダンス。
スポーツ: 円盤投げ、走り高跳び、棒高跳び、バレーボール、ハードル走、砲丸投げ、馬術競技、飛び込み、槍投げ、バスケットボール、サッカー、オートバイ競技、走り幅跳び。
中国の手品師の路上パフォーマンスを観ている幼い子供たち。
機械を使って減量に取り組んでいる肥満の女性たち。
実験映画としての側面
本作は、多重露光、低速度撮影、スローモーション、逆回し、フリーズフレーム、マッチカット、ジャンプカット、スプリットスクリーン、ダッチアングル、超接写、トラッキングショット、ストップモーション・アニメーションなどのさまざまな映画技法を駆使している。
前衛的なモダニズム映画としての側面
本作は未来派やロシア・アヴァンギャルドの影響を受けた前衛的なモダニズム映画でもある。
本作における近代の機械文明と工業都市への賛美には未来派からの影響が見られる。
本作の幾何学的な構図と抽象性は構成主義などのロシア・アヴァンギャルドの美術からの影響を示している。
プロパガンダ映画としての側面
1917年の十月革命後の1919年にウラジーミル・レーニンはソ連の映画産業を国有化した。レーニンは映画を「最重要の芸術」と捉え、宣伝・扇動・教育のための手段として重視した。
この歴史的状況の中で、本作はソヴィエト市民の愛国心を鼓舞し、彼らを団結させるためのプロパガンダ映画として制作された。
本作が描いているソヴィエト連邦はむき出しの真実ではなく、美化されたイメージである。
人々が余暇活動を楽しんでいる本作のショットは、ソヴィエト市民の生活がいかに素晴らしいかということを示している。
メタ映画としての側面
『カメラを持った男』はメタ映画、すなわち映画それ自体を題材にした自己言及的な映画でもある。本作は撮影、編集から劇場での上映に至るまでの映画の制作過程の描写を含んでいる。
本作は劇場で映画の上映が始まる場面で始まる。映写技師が映写機を操作する。観客が入場する。上映開始とともにオーケストラが演奏を始める。
本作の撮影を担当したミハイル・カウフマンが劇中でカメラマン(カメラを持った男)として登場する。カメラマンは手回しカメラと三脚を担いで車でソヴィエトの各都市を移動して回り、さまざまな場面を撮影する。
本作には、本作の編集補佐を務めたエリザヴェータ・スヴィーロワがカッティング・ルームで映画を編集している場面も含まれている。
本作は観客が劇場のスクリーンに映写された映画を観る場面で終わる。
受容と影響
本作は公開当時はソ連の内外で酷評されたが、1960年代から1970年代にかけて世界的に再評価が進み、現在では多くの批評家たちによって史上最高の映画の一つとして高く評価されている。
ヴェルトフの影響を受けたジャン=リュック・ゴダールは1960年代末から1970年代初頭にかけて、「ジガ・ヴェルトフ集団」名義で政治的な映画を制作した。
ゴッドフリー・レッジョが監督したアメリカ合衆国の実験的なドキュメンタリー映画『コヤニスカッツィ/平衡を失った世界』(1982年)はスローモーション、低速度撮影などの映画技法を駆使しており、本作からの影響がうかがえる。
本作は2012年にイギリスの映画雑誌『サイト&サウンド』の「史上最高の映画」の批評家による投票で8位となった。
2014年には『サイト&サウンド』誌の「批評家が選ぶ史上最高のドキュメンタリー50」で本作が1位となった。
2021年にウクライナの国立オレクサンドル・ドヴジェンコ映画センターはウクライナ映画史における映画ベスト100のリストで本作を3位にランク付けした。
サウンドトラック
多くの作曲家やミュージシャンたちが『カメラを持った男』のサウンドトラックを独自に制作している。
アロイ・オーケストラ
1995年にイタリアのポノーネ無声映画祭で本作の復元版が初上映された際に、ケイレブ・サンプソンがヴェルトフが書いた音楽指示に従って作曲したオリジナルの音楽スコアがアメリカの音楽アンサンブルのアロイ・オーケストラによって演奏された。
ゲイル・イェンセン(バイオスフィア)、ペール・マーティンセン(メンタル・オーヴァードライヴ)
1996年にノルウェーのエレクトロニック・ミュージシャン・作曲家のゲイル・イェンセン(別名バイオスフィア)とノルウェーのテクノ・ミュージシャンのペール・マーティンセン(別名メンタル・オーヴァードライヴ)が作曲したサウンドトラックがノルウェーのトロムソ国際映画祭で使用された。イェンセンはヴェルトフが書いたピアノ伴奏者向けの指示を参照してサウンドトラックの半分を作曲した。
イン・ザ・ナーサリー
1999年にイギリスのネオクラシカル・ダークウェイヴ/マーシャル・インダストリアル・バンドのイン・ザ・ナーサリーがイギリスのブラッドフォード国際映画祭のためにサウンドトラックを制作した。
ザ・シネマティック・オーケストラ
ジェイソン・スウィンスコーが作曲したサウンドトラックが、2000年にポルトガルのポルト国際映画祭でイギリスのニュージャズ・電子音楽グループのザ・シネマティック・オーケストラによって初演された。
マイケル・ナイマン
英国映画協会(BFI)はイギリスの作曲家のマイケル・ナイマンに本作の上映中に生演奏される音楽スコアの作曲を委嘱した。ナイマンはヴェルトフの音楽指示を参照せずに、自身がセガサターン用のビデオゲーム『エネミー・ゼロ』(1996年)のために作曲した音楽を再構成してスコアを制作した。ナイマンのスコアは2002年にロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールでマイケル・ナイマン・バンドによって初演された。